�������瑖���A�ω���߂���
����31�N�i2019�j4�����{�A�V�c�É����ʂ̓����j���ƂȂ��̏�ŏ\�A�x�ƂȂ�����^�A�x�̑O���B�D�V�Ɍb�܂ꂽ�U�����a�̈���A���{��s���Ɏc��y�؈�Y�Ȃ��ł������R�̌R���v�Lj�Ղ���Ƃ��ď�������B�܂��͉��{��`���̖��l���A�����i���邵�܁j�ցB��������߂�����͘H���o�X�𗘗p���đ����i�͂���݂��j�����n�A�ω���������Ă����B
1�D�O�}�V�����牎���v�ǁE���R�u�����p�v�ǁv�̎���

����7��50������A���}�E���{�ꒆ���w�����̕��s�҃f�b�L�B�w����O�}�V���ւ͕�����15���قǁB

�f�b�L���猩���낷�ʂ�̉E�������ւƐi�ށB
�O�}�V���ւ͏Ó�M���̊p���E�܂��A�s�����O�����̊p�œ˂������鍑��16�������܁B����16���E���쒬�����_���E�܂��ăt�F�j�b�N�X�̗������Ԓʂ���}���V�������������ԑ��̕��������ɐi��ł����A��������܁B

�E��Ɏp��������O�}�̃}�X�g�B

�O�}�V������̘A���D�B���ւ͒�8��30���̏o�q�����A8���߂��ɓ��������Ƃ��딭�����͊��ɒ��ւ̗�B����Ȃ��Ă��\��Ȃ��̂ŁA����͂���ł����B

�L�O�͎O�}�B�O�}�͓̊����w��������̃y�[�W�ցB


�A���D�^�s��Ђ̐E������Ɍ������A�o�q�B

�O�}�̗Y�p�B

�����ւ�10���قǁB

�Y�[���łƂ炦��h�g��ԓ���z���̉��l�݂ȂƂ݂炢�E�����h�}�[�N�^���[�i296m�j�B

���{��s�X�̌������Ɏp��������x�m�R�B

�����V������㗤�B

��D�����̂́u�V�[�t�����hZero�v�B���Ȃ�100���ゾ���`���̕����i�ւ������j���ł���Η������̏�q���܂߂�240���߂���D�ł���B

�C�R�`��B�u�����Ă݂悤���{��̌R����Y�v���[�t���b�g�i���{��s�j�ɂ��Ɩ���10�N�i1877�j�ɊC�R���Ǘ�����`�͈̔͂��������̂Ƃ��ď��オ���Ă��A����16�N�i1883�j�Ɍ��݂̐Β��Ɍ��đւ���ꂽ�B
�����v�ǂ͖����O���ɗ��R���NJ������v�ǁB���̖����͊ω���E�����i�͂���݂��j�E�x�Ái�ӂ��j�̖C��ƂƂ��ɓG�͂̓����p�ւ̐N����h���u�����p�v�ǁv�̈ꗃ��S���ƂƂ��ɁA�R�`���ӂ̖C��ƂƂ��ɉ��{��R�`�ւ̐N����h���������S�����B

�d�C���@�֎Ɂi���d���j�B�ΒY��p�������C�@�ւŃ^�[�r�����Ĕ��d�A�e���ɓd�C�����������B
�ǂɂ̓����^�����h���Ă��邪�ē��ɂ��Ǝ��������K�ǂ̍\���Ƃ̂��ƁB

���˂͉��n�̃����K�ς�������Ƃ���������B�Ǘ����̓W���p�l���ɂ��ƁA���d���̃����K�ς̓C�M���X�ςɂ�������ȃI�����_�ςƂ����������ςݕ��炵���B

�����A�v�ǐՂ̎U��ցB

�ÊD��̊�Ղ�����Đؒʁi����ǂ����j���ʂ���A�I�V�̒ʘH�ɂȂ��Ă���B���̐�͗����ɐΑ��E�������̗v�ǎ{�݂��\�z����ĖC��̗ۓ��ƂȂ��Ă���B
�����̗v�ǂ͖���14�N�i1881�j�ɋN�H�A17�N�i1884�j�v�H�B�ω�����A���C��Ɏ������H�ł��蓌���p�v�ǂɂ����鏉���i�����O���j�̈�\�ƂȂ�B
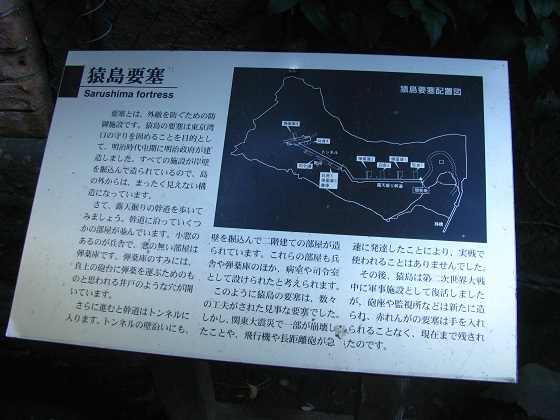
����B

�C��̗ۓ��ɐ݂���ꂽ���ɁB���ɂ͎ߏ�ɏ������t���Ă���B

���ɂ̓����B

���ɂ̏����B
�����̐ςݕ��͓����i�ɗ����̒���i�Ȃ��āB���Ӂj�Ə����i�������B�Z�Ӂj�����݂ɕ��ׂ�A�t�����X�ρi�t�����X�Â݁j�B
�̐ςݕ��̓����K�̂悤�ɒ����������t�����X�ς̂悤�ɕ��ׂĐςށA���m���̐ςݕ��B����͖������疾���̏����ɂ����ĉ��l�̋����n�Ƃ�킯�R��i�O���l�͎R����u�u���t�v�ƌĂj�E�G�ł�����ɓ������ꂽ�ςݕ��Łu�u���t�ρi�u���t�Â݁j�v�Ə̂����B�u���t�ς͂��̌㏺�a��������܂Ŏs�X�n�̊e���ŗp����ꂽ�B
�����̃t�����X�ρE�u���t�ς̍\�z���͖����O������̂��̂����ɂ悭�c���Ă���B�吳12�N�i1923�j�̊֓���k�Ђł͂���܂ł̓y�E���z�\�����������e�n�ő�Ō������������v�ǂ͌R���{�݂Ƃ������Ƃ������Ă��A���ɋ��łɑ���ꂽ�̂��낤�B

�ۓ��̔��Α��ɂ͒��߂ɐ����̃u���t�ς������Ɏc���Ă���B

�����Ēe��ɁB�ۓ��̏�ɂ͓�������24�p�J�m���C�i���_�C�Acannon�j�l�傪�����t����ꂽ�i���C��j�B
�������̉����C��͓G�͂Ǝ���������邱�ƂȂ��������I�����B����������͖c��ȗ\�Z�𓊂������ʂȔ������������Ƃ����A�����Ă����ł͂Ȃ��B
�����A���I�푈�ł̓E���W�I�͑������{�̉��C�ɏo���B�A���D�������A�\�߂��Ȃ��瓌���p���Ɍ��ꂽ�B�������E���W�I�͑��͓����p�v�ǂ̖C��ƌ�킷�郊�X�N��`���Ă܂ŁA�p���ɐN�����悤�Ƃ͂��Ȃ������B���ɋ��łȗv�ǂ��\�z����Ă��Ȃ���Ί͑��͓����p�ɐN�������{��R�`�≡�l�`�A��s�����Ƃ������d�v���_�ɖC���������ĉ̊C�ɂ����ł��낤����A�C��̗}�~�͂͂�����Ȃ��������ꂽ���ƂɂȂ�B
�Q�l�u�V���{��s�j �ʕ� �R���v

24�p�J�m���C�B
�摜�o�T�u�V���{��s�j �ʕ� �R���v

���ɁE�e��ɂ̕��тƔ��Α��̕ǂɒz���ꂽ�����\�z���B����͉������i������ԁB�Ҕ����j���낤���B�����K�ǂɂ͔݁i�Ђ����j���˂������ʂ����߂̌��̂悤�Ȃ��̂��J���Ă���B�������A�������Ƃ��Ă��݂��˂��������ł͊��I����g�����Ҕ����Ƃ��Ă͐S���Ȃ��̂ŁA����ς艽���ʂ̗p�r�̂��̂��낤�B
�����̐ςݕ��͒������ׂ��i�Ə�������ׂ��i�����݂ɐςݏd�˂�C�M���X�ρB�Ǘ����̓W���p�l���̉���ł́u�C�M���X�ρv�Ɓu�I�����_�ρv�̈Ⴂ���������Ă��邪�A�����̐ςݕ��͑傫�ȉ摜�Ŋm�F����Ƌ��Ɂu�r㻗����v���p�����Ă���B
�Ȃ��Ǘ����̓W���p�l���ɂ́u���C��w�ߏ��t�����v�ȂǂɃC�M���X�ςƂ�������ȁu�I�����_�ρv��������A�Ƃ���B

�����ʂĂ���\���B

��������e��ɁB


����B
�e��ɂƕ��ɂ́A�l�E���l���O���[�v�����̓����\�����Ń{�����e�B�A�K�C�h�̕��̈����ɂ������ɓ����Č��w���邱�Ƃ��ł���B
����͉����v�ǂ̌�Ɋω���C��܂ʼn��\��ŎO�}�V���ɖ߂�D�̎��Ԃ����߂Ă������߁A���w�I�����Ԃ����킸�Q���ł��Ȃ������B

�e��ɂ̓����B�V�䂪���H�[���g�V��i�J�}�{�R�^�̓V��j�ɂȂ��Ă���B

���Α��̊R�̗����\�z���B�A�[�`�̓������t���Ă���݂̗���ʂ��炵�������J���Ă���B���邢�͊Ǘ����̓W���p�l���ɂ݂鉎�����ʐ}�ɍڂ��Ă����u�֏��v�������̂��B

�t�����X�ς̓������͂�����ƕ�����B

�A�[�`���͍ǂ���Ă���B

�ۓ��̉��͓V����J�킹���Ɏc����詓��i�g���l���j�ɂȂ��Ă���B
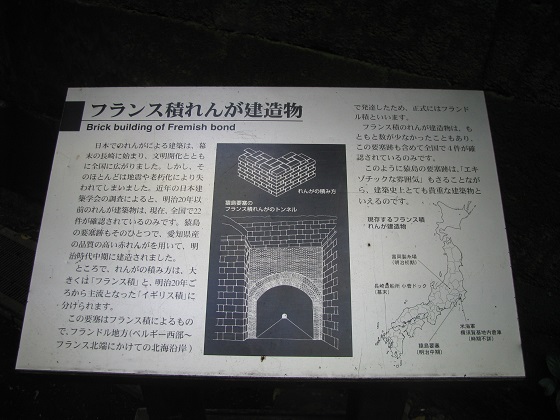
����B
������ł��邪�A�����R�̊֘A�Ō����ƃ����K�\�����͖���20�N��������Ƃ��ăt�����X�ς���C�M���X�ςɕϑJ���Ă������B
�����R�W�ȊO�ɖڂ�]���Ă݂�ƁA����ȍ~�̎���ł��t�����X�ς͏��Ȃ��炸�p�����Ă��邪�A������ɂ��Ă�����20�N����܂ł̃t�����X�ςɂ�郌���K�������͊��S�Ȍ`�Ŏc���Ă�����̂͂����킸���B
���Ƃ��Ή��l�̏ꍇ�A�R�������������n48�Ԋفi�����\������j�����l�ŌÂ̋����n�������i����16�N�E1883�z�j�Ƃ��ăt�����X�ς̎c���������ۑ�����Ă���B������͊֓���k�Ёi�吳12�E1923�j���o�ď��a�����ɉ��C�H�����{����Č����Ƃ��ė��p����Ă������A����13�N�i2001�j�ɋ���ɋ߂Â��邽�߂̕ۑ��H�����{����ĉ��C������P���B���݂͐k�Ј�\�̂悤�Ȏp�ƂȂ��Ă���B����A�t�����X�ς̍H�@���̂��吳���Ɏ����Ă��������ɗp�����Ă�����Ƃ��āA������w�i�����r�܁j�̗����Z�ɌQ������B

�A�[�`�����̋Ȗʂ͏����̕��тɂȂ��Ă��邪�A�[�`�̒f�ʁi���ʁj�͒���̕��т����łȂ��t�����X�ς̒���E�������݂̕��т������A���Ȃ蕡�G�Ȑςݕ������Ă���B

�g���l���̓����B

�V��B�����̕��ԋȖʁB

�g���l���ǖʂ̏o�����B

�g���l�����̒n���{�݁B�g���l�����ɂ͕��ɂ�e��ɂ̑��Ɏi�ߕ����u����Ă���A�v�ǂ̒����������B

�����Ζʂւ̏o���B
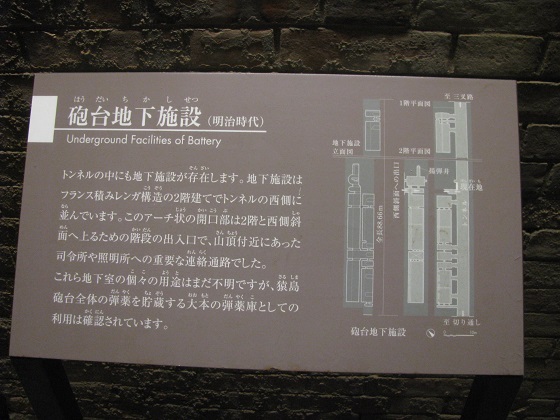
����B

�g���l���̏o���B

�o���̓˂�����͗��R�ɂ��v�ǂ��\�z���ꂽ�����͒e��ɂ������B�㕔�ɂ͓��k������27�p�J�m���C��傪�����t����ꂽ�i���C��j�B
�吳12�N�i1923�j�̊֓���k�Ђł͂��̌��S�ȗv�ǂ���ЁB�����ČR�͓��m���C��������퓬����q��@�ɂ��U�����䓪����Ƃ�������̐����ƂƂ��ɉ����C��͖C��Ƃ��Ă̕K�v�����ቺ�B�吳14�N�i1925�j�ɂ͖C��͔p�~���ꏜ�Ђ����B���a2�N�i1927�j�ɉ����v�ǂ͊C�R�ֈڊǂ��ꂽ�B

�o�����o�ĉE���̗ۓ��B�����͑f�@��̐ؒʂ̂܂܁B

�ۓ�����詓��i�g���l���j�̐�́A�W�]��̂���L��֒ʂ���B������̃g���l�����v�ǂ��\�z���ꂽ��������̃g���l���B���̓����ɔ�����ʘH�������B
�E��̃����K�ǂɂ͕����̏o����������B
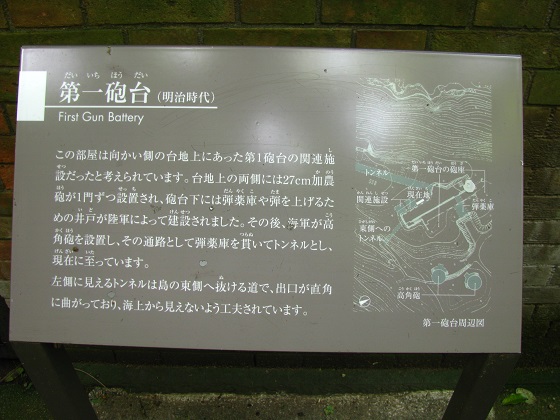
�ē��ɂ́u���̕����͑��C��̊֘A�{�݂ł͂Ȃ��������v�Ƃ���B

�o���̐��ʓ˂�����Ɍ�����A���C�䉺�̃g���l���B�e�ɊK�i��������B
������̃g���l��������ꂽ�̂͏��a�����B�����v�ǂ̊NJ������R����C�R�Ɉڂ����̂��ɗ��R����̒e��ɂ��т��đ����A�C�R�̍��p�C�C��ւ̒ʘH�ƂȂ����B

���ʂ̃g���l�����A�C�R���p�C�̖C��ՁE���@���A�̕��ʂցB
�Q�l�u�V���{��s�j �ʕ� �R���v

