�a��u�˂Ɛ`��~�n�N���Q�߂���
����29�N�i2017�j�̑�^�A�x�O���B�\�O��i������ ����j�̓�[�E�`��i�͂��́j�~�n�̓쑤�ɗ��N����a��i���Ԃ���j�u�˂��߂�������A�`��~�n�N���Q��k���i�������j�A�����R�i����������܁j�Ȃǂ�K���B
2�D�a��u�˂��瓪���R��
�a��u�˂���u�˂̐����A�n�C�L���O�D�K�n�̓����R�ցB�����R���ӂ̐瑺�n��͐H�p�̍��Ԃ͔̍|������B�����R����͔��R�_�ЁA��|�̐�Ə���A�a��w�ցB�R�y�Y�͐`��̑����E����X�́u�����ہv���āB
1�D�N���Q���甒����ׁA�k���ւ͂�����B


�`��s�E�ȌE��ّO�̓��W�B�������瓪���R�i����������܁j�������B�����R�����ւ́u�����R�ߓ��v�̕����ւƐi�ށB
�Ȃ����W��i�́u�����R�����v�̕����͏a��w���ʂ։���Ă����ēo��Ԃ��Ƃ�������ȃ��[�g�B


���ʂ̋������ւƐi��ł䂭�B


�������������B


���W�̂ق��A�Â�������ׂ�������B���͓ȌE�_�Ђւ̓��B


�u�E �ӂ��� ���c�����v�ƍ��܂ꂽ������ׁB��O���ɂ́u�\���s�ꓹ�v�A�����ɂ́u�� ��ԑ匠�����v�Ƃ���B
��O���́u�\���s��v�Ƃ͐`��̒��S���ł��鋌�]�����̕ʏ́B�s�i�����j������������A�]���̂�����͉��҂������o�ϊ����̒��S�ƂȂ��Ă����B
����A���́u��ԑ匠���v�Ƃ͓ȌE�_�Ђ̋��́B��ԑ匠�����J��ȌE�_�Ђ́A�]�ˎ���ɂ́u��Ԑ_�Ёv�Ə̂����B���݂̖��͖̂����ɓ����Ă���̂��́B
�����܂ł��ǂ��Ă����������́A�]�ˎ���ɕx�m�u�E��R�u�̐l�X���s���������Ó��ł������B
�Q�l�u�O�� �R�̂��̂�����v�`��s���s�B


�ؒʁi����ǂ����j�̓����ւƐi�ށB�Ó��̕��͋C��F�Z���c�����B


�Ó�����̑�R���܂��i�ʁB


�R����i�ށB


�Ԃ������̉��Ɂu�F��R�i���R�j�̔������l�v�Ə̂��鏬���Ȃ��Ђ��J���Ă���B


�|�т��Ă䂭�B


����ɔ������R�i�₭�ɂ݂�܁j�ւ̓�����ܑ��H�܂ŗ����B


�������R�ւ͎���̈ē������Ă��Ă���B
�ǂ���甪�����R�̐�ŁA��قǂ���̗��ĊŔ����m���鑢���H�����s���Ă���悤���B


�ܑ��H��i��ł䂭�ƍ���ɓ�����B�E���i�ނƏa��w���ʂ̎s�X�n�ւƉ����Ă䂭�B���W�����Ă��Ă���A�����͍����i�ށB


���W�ɏ]���č����i�݁A�����R�ցB


���z����O��ʉ߁B


����i��ʁj�ɒi�X���̔_�n���傫���J���邠����܂ŗ����B


�p�b�`���[�N�̂悤�ɍL����A�i�X���B


���i�ɔ����̓�q�R��]�ށB


�̉Ԕ��B


���R�̌����i���傫���L����Ȃ��A���n��̏W���������낷�B���Ձi�̂ǂ��j�ȁA�����i�F�B




��i�ނƍĂѕ\�O��̒��]���J�����B
��ʉE�̓��m�x����犄�R�ŁA�������x�𗎂Ƃ��Ğw�x�i�Ђ̂��������j�R�łƑ����B


���x�𗎂Ƃ����ƕ��̌������ɐ��O��̗Y��E�w���ہi�Ђ̂��ڂ�܂�B1601m�j�����̂����₩�ȎR�e���͂�����Ƃ̂�������B�a��u�˂���u�ڂ�܂�v�������܂ł͂����茩����Ƃ́B


����B�Ⴄ�`���̓��W�����ꂽ�B�����R�ւ͉E�������B
�����ō��Ɂu�a��w2.7�q�v�Ƃ���̂́A���o�X��̂���W���։���ē��g���l�����铹���s�����[�g�B������͓��o�X�₩��o�X�����p�ł��邪�{���͏��Ȃ��B


���������A��قǒʂ��Ă������z���ꂠ����̕���܂Ŗ߂�����ɂ��u�a��w2.3�q�v�̕\�L������B������̓g���l���̖k���ɉ���郋�[�g�B�����ɂ͂�����̕��������I�ɋ߂��B
�����āA��ɂ���āu�a��w�i�����R�����o�R�j�v�̓��W�B�����́u�����R�����v�܂ł̋����\���͐�قǂ܂ł̓��W�̋����\���Ƃ̘A�����͂Ȃ��B������0.5�q�͑Ó��Ȑ����B
�ȌE��قł́u�����R�����v�܂�3.2�q�i����͎s�X�n�։���Ă������p���w���Ă����j�B�ȌE��ق��炱���܂ł͂��悻1.5�q�B�P���Ɉ����Z����Γ����R�����܂Ŏc���1.7�q�ɂȂ�͂������A�����œ��W�̐����������R�����̑�����v�����������ɂ���ւ���Ă���B
���������ȌE��ق���s�X�n�ɉ���Ă����ĕʃ��[�g�����ǂ��Ă���A������̃��[�g�̒��Ԓn�_�ł͂Ȃ������̐����͓ȌE��قł̓����R�����܂ł̋���(3.2�q)�Ƃ͖��W�Ȃ̂ŁA����ւ�莩�͖̂��Ȃ��B
���Ƃ�����A���W�̌`����ύX���邱�ƂȂ����������A���������邩�̂悤�ȑ̍قł���ւ�����������ڂ���̂́A���܂�e�Ƃ͌����Ȃ��B���W���������茩��T�d�Ȑl�قǁA�����Ă��铹������ł悩�����̂������Ȉ�a���������邩������Ȃ��B
�Ƃ����킯�Ők�����瓪���R�ւƕ����ꍇ�A�k���o�X��߂��̓��W����ȌE��ّO�̓��W�܂łɂ��Ắu�a��w�i�����R�����o�R�j���q�v�͕\�����̂����āu�����R�������q�v�̐����͋C�ɂ��Ȃ��̂��悢�B
�ȌE��ّO�̓��W�ɂ��Ắu�����R�������q�v���̂��������āu�����R�ߓ��v�ɏ]���ĕ����ΊԈႢ�Ȃ��B
���x�������Ă���l�ɂƂ��Ă͖�Ȃ����Ƃ��낤���A���߂Ă̐l�i�R�����̌o���̐l�j�ɂƂ��Ă͂�����ƔY�܂������W�������낤�B




�`��s�瑺�i���ނ�j�n��̐l�����̎�ɂ��u�T���K�j�̗��v�Ƃ������R�̌��L�ꂪ�����Ă���B


�E��ɑ�R�A�^�ɎO�̓��B


���̕���B��`���̈ē��}�b�v�������Ă���B


���͐��[���R�B�����R�͂�������E�������Ă����B




�����Ɣ����`���ɕ����Ă����̂ŁA�����ł����Ԃ�Ɖ����Ă��܂��悤�Ɋ�����B���������̂̓n�C�L���O�K�C�h�}�b�v�����ł͕�����Ȃ��B


���������Ă����Ɗ剹�i���肪�ˁj�_�ЂƁu���肪�˂̏��v�̓`���ē�������B
�Ȃ��n�C�L���O�K�C�h�̃R�[�X�}�b�v�ɂ́u���肪�˂̏��v�̈ʒu�̕\��������Ă��܂��Ă�����̂�����B�����Ȃ�ƕ���̈ʒu���̔c���ɍ����𗈂����ƂɂȂ�̂ŁA�ЂƂ̃K�C�h�}�b�v���L�ۂ݂ɂ��Ă��܂��̂͂��܂肨���߂ł��Ȃ��B
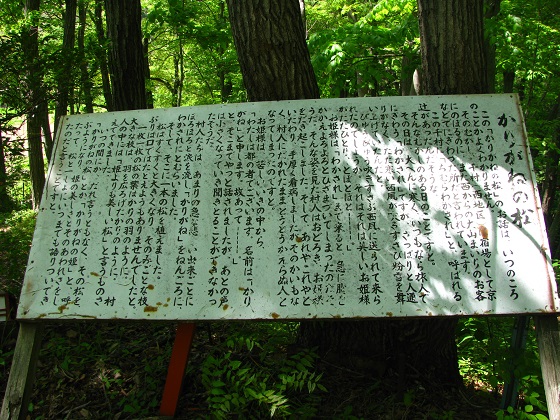
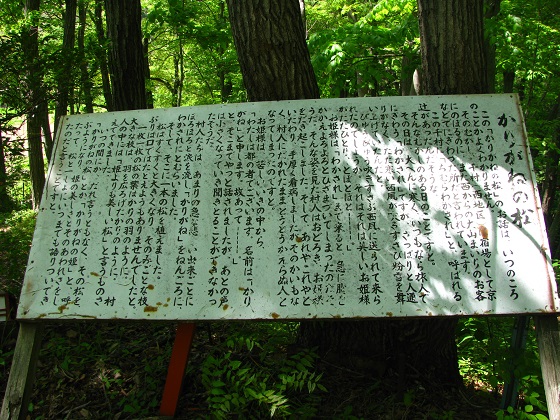
�ē��B
�Ó��������ւƉ��������R�u�E�x�m�u�̐l�X�œ�����Ă������̐́B���ᐁ�������Ԋ����̒��A�s�������ė����u���肪�ˁv�Ɩ����P�����̒n�ŗ͐s���A���₦���B
���l�͕P������݈�{�̏���A���Ē������B�₪�Ă��̏��͔������}�U��ɐ������A�������u���肪�˂̏��v�ƌĂ��悤�ɂȂ����A�Ƃ���B


�剹�_�Ђ͕����ɕ���ꂽ�������K�B�`���̏��́A���Ɏ����Ă��܂����悤���B


�u�����R�����v����܂ʼn����Ă����B


���֍s���Ɠ����R�i����������܁j�A�E�։���Ɣ��R�_�Ђ��o�ďa��w�ցB


���o�X�╪���肩�猩������悤�ɂȂ����u�x�m���ˁE���d���R�[�X�v�Ƃ������W�B


�k���o�X�₠���肩��ڂɂ��Ă����`���̓��W�͂Ȃ��B
����ɂ��Ă��k������ʂ��ŕ����Ă����l�̂��߂ɁA�����܂ł�������̓��W�𗧂ĂĂ����̂����瓯���`���Łu�����͓����R�����v�̓��W�𗧂ĂĂ������ق����n�C�L���O���S�҂ɂ͗D�����悤�Ɏv���B


���d�����������B
���̂�����i�`��s�瑺�j�͐H�p���ԁi���̉��Ђ��j�͔̍|������ȂƂ���B�����R�̃n�C�L���O�R�[�X�ɂ��n�C�J�[�̖ڂ��y���܂��鑽���̃��G�U�N�����A�����Ă���B


�����R�ւƓo���Ă����B


����ݐ[���Z�g���̔��d���͉��|��́u�֎R�i����j�v���B


������͒W�g�F�̃��G�U�N���B


�u�F��̋u�v�̍�����i��v�҈ԗ��j���߂��Ă����B


���R�ȓ��������B


����R���͑��d���S���ւ̍�ƘH�̂悤���B�����͍��ցB


���̓��͑�䒬�i�������܂��j�E�̃��K�\�[���[�i�������쏊������Ւn�j������։����Ă������炵���B���x�͉E�ցB
���̂悤�ȓ��̓n�C�L���O�}�b�v�ł͏ȗ�����Ă��܂��Ă���B�����������Ƃ���ɂ���
�u�������R�v�Ƃ������W�𗧂Ă�̂��e�̂悤�ȋC������B


�u���d���̗��v�B���n�p�̖��͔|����Ă���B


�W�]�}�̂���W�]�n�B
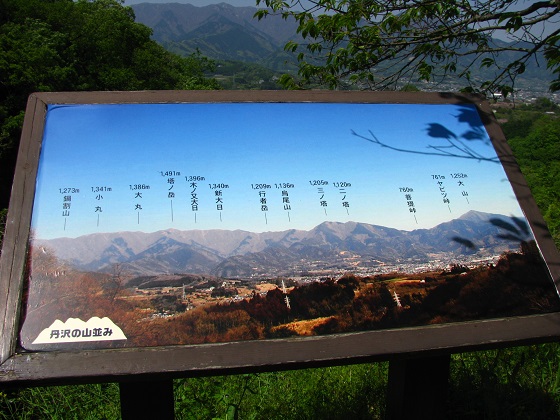
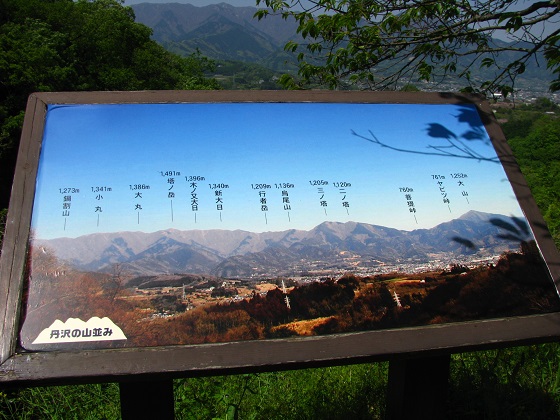
�\�O��̑�W�]�́A�����R��������̃n�C�L���O�R�[�X�ł͐���̒��߁B




�ЂȒi��̋x�e�L��B


��i�ɂ̓g�C���i�L���j�Ⓦ��������B


�瑺�͉��Зp�̐H�p���Ԃ̎��n�őS���V�F�A�̔����߂����߂�Ƃ����B�������Ǝ҂̍���A��p�ҕs���͂����ł���͂�؎��Ȗ��ƂȂ��Ă���B


�R�����������͂��炭�i�ނƍ����A�E���ɕ������B


�����֍s���ƁA�����ɖؒi�̓o��B




�R�����J���Ă���A�H�t�_�ЁB


�H�t�_�Ђ͐̏������K�B
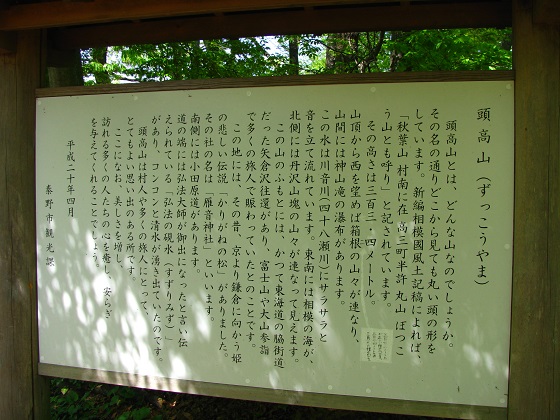
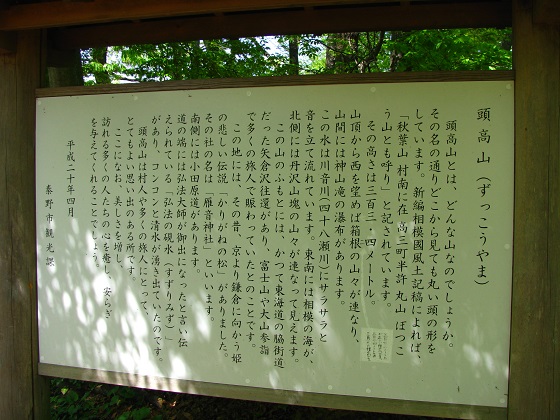
�����R�i����������܁A������������B�n���@�n�`�}�̎O�p�_�̍ŐV���l��303.3m�j�̈ē��B
�����܂�ł����̑�x�e�����B


���R�͉E���̓��ցB


�Ȃ��炩�ɉ����Ă����B������͏H�t�_�Ђւ̏���A���H�͒j��Ƃ������ƂɂȂ�B


�R���������悤�ɍ����E�E���̕���ɖ߂�B


�x�e�L��̂�����ɗ��_�R��i������܂����j����̓��W�B
���̂Ƃ��͏ڍׂȒn�`�}���������킹�Ă��Ȃ������̂ŗ������Ȃ��������A�n���@�n�`�}��������肩�Ȃ�}�ȓ������邱�ƂɂȂ�悤���B���W�ɂ�������Ə�����Ă���40���Ƃ������Ԃ͂�������̉����ɂ����鎞�Ԃ��낤�B


���H�͉E��̓��������牺��Ă������A���H�͔��R�_�Ђւ̋ߓ��ƂȂ�̂ō����s���B


�ؒʂ̓�������B


�ԓ��ɍ����B
�����Ă���ܑ��H���E�֏オ��ƁA��قǒʂ��Ă����u�����R�����v�܂Ŗ߂邱�ƂɂȂ�B


�܂�Ԃ��悤�Ɏԓ��������Ă����B


�����Ă����Ƃ����ɍ���Ɍ�����A���R�_�Ђ̒����B���̑�����т��Ă���B


���Ȃ���̖��ؕS�I�ɑI�肳��Ă���A���R�_�Ђ̃X�M�B������44m�Ƃ��Ȃ荂�������̊��Ɋ��̋������͂�5m�ɖ������A���Ȃ�ق����肵����ہB


�Q���Βi���オ��A�q�a�ցB


�q�a�B�J���Ă���_���܂͏��_���܂̈Ɏדߔ����i�����Ȃ݂݂̂��Ɓj�A���R�M�̍Ր_�ł���e���䔄���i������Ђ߂݂̂��Ɓj�B


���i�ނˁj�ɂ���������́u��ɓ��̊ہi��Ɍ��ہj�v�B


���ɂ͐����ɍ킪�ꂽ��i�����j���ڂ��Ă���B�����ɂ������_���܂��J��_�Ђɂ悭������`���B
���q�i�����͂��B����o���������j����富ҁi������܂��j�ɂ͗��̒����B���ԁi���܁j�ɂ��ׂ��Ȓ������{���ꂽ�A�]�ˎ������̌��z�B


���ɂ͖{�a�����܂��Ă���B��������]�ˎ������̒z�B


�_�y�a�i������ł�j�B


���ؗ��̎Бp�тɈ͂܂ꂽ�A���R�_�ЁB
���R�_�Ђ���ɂ��āA�N���u��|�̐�v�ցB


�ԓ��������Ă����ƁA���ʂɓ��{�z�[����������B


����ɐi�ނƕ�n�ɗ��ω���F���B


�˂�����̎�O�E�肪�A�N���u��|�̐�v�B


����̐`��~�n�N���Q�߂���̍Ō�ƂȂ��|�̐�͎���̌�����Ɉʒu����B���̗N���͏��߉���˂Ƃ��Č@��ꂽ���̂����݂̌`�ɐ������ꂽ�A�Ƃ��������e���L����Ă���B


��|�̐�a��w�������B�茳�̓��ނ̃n�C�L���O�K�C�h�}�b�v�ƏƂ炵���킹�Ă݂Ă������͂����肵�Ȃ��������A�����܂ň����Ԃ��̂��ʓ|�Ȃ̂łƂ肠�����˂���������ցB


�ɂ����A���ցB






����Ă�������̕����ꓹ�B��Ŋm���߂�ƍ��͐瑺�z����֒ʂ��铹�������悤�����A���̂Ƃ��͌��ݒn��������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�ǂ����K�C�h�}�b�v�̓��Ƃ͈Ⴄ�B
��͂肠�����������ɂ͖ʓ|�������炸�ɎR���Ȃ�n���@�n�`�}�A�܂��Ȃ�Yahoo�n�}�Ƃ��̉�ʂ�K�v�ȕ����ׂāuF11�v�L�[�Ńt���X�N���[���\���ɂ��āuPrtSc�v�L�[�ŃR�s�[���u�y�C���g�v�ɓ\��t���Ĉ���A������������ł����������g���₷���B
�����͊��ʼnE�֍s���B


���̕����ꓹ�ɂ́u���̐�s���~�܂� �ʂ蔲���ł��܂���v�̈ē����f���Ă���B�ē��ɏ]���A�E�ցB


���ʂɛ����̂悤�ɂǁ[����ނ����R�Ȃ݂��������B����Ȃ�������Ƃ͖����B���߂Ȃ��牺���Ă����B


���炭�s���ƃo�X��u�����v�B�o�X����߂��Ă�����������ł��傤�ǃo�X���ǂ������Ă������B


�o�X�̌��ǂ��悤�ɍs���ƁA�E���Ɏ��̃o�X��B
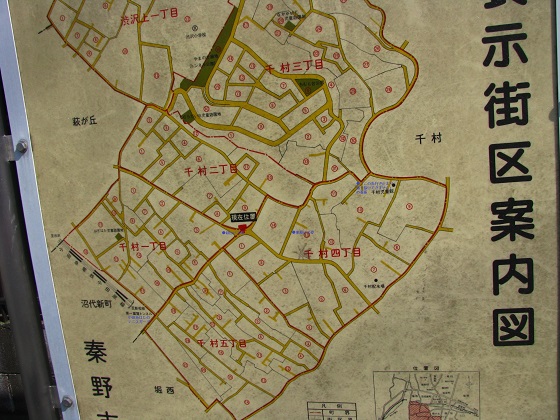
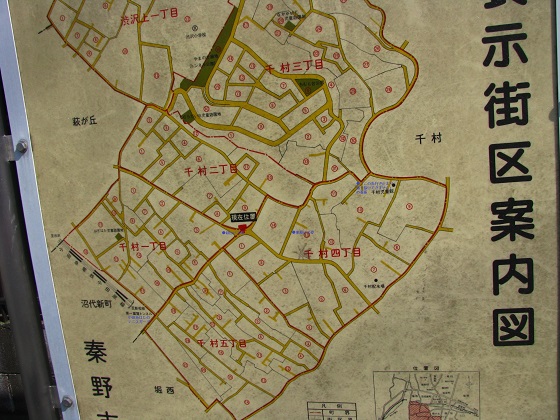
�X��ē��B�@�g����i�������H�̓T�C�g�Ǘ��ҁj�B
���H�����ւ̋ߓ����m�F����B


�o�X��Ƃ͈Ⴄ�����i��ł����B


�Ăѐ��ʂɎR�����Ȃ���A���炾��̉���B


�u���c�}�͂��̃e�j�X�K�[�f���v�̊ŔB


�e�j�X�K�[�f���̉��͐`��~�n�̐V���c���o���ƂȂ�g���l���ɂȂ��Ă����B���Ƃ͐��H�����ɐi�ށB


���Ȃ�ɐi�݁A�R���r�j�̊p�����܂���Ήw�͂��������B


���؎�O���E�܁B


�w�O�ʂ�̎����ō���̎R�y�Y���w���B

�`��̑����u����X�i���˂����ゼ���Ă�j�v�́u�����ہi���炳���Â݁j���Ď��v�l���r�B���x���f�U�C���͂��̊Ԃɂ��V�������̂ɕς���Ă����B���̖��킢�́u�\�t�g�Ȑh���v�Ƃ�������ہB
�u�����ہv�̖��́A����̎R�����ōŏ��ɖK�ꂽ������א_�Ђɂ��Ȃ�ł���B


�a��w�ɓ����B
���̃T�C�g���i���jACES WEB �u�V���E�X2�v�ɂ��쐬���Ă���܂��B
