���˔����{�E�����R���狌���C�����ˏh
����28�N�i2016�j��7����{�A���˔����{�A�����R�̗m�ق��狌���C�����ˏh�E�G������B
���˂̎s�X�n�͑��B��̑�́E���͐�i�n����E�ɂイ����j�ƁA��R�̓�ʂɌ�����t�x��i�͂邽������j���痬�ꉺ�������ڐ�i���Ȃ߂���B�Ԑ���E�͂Ȃ݂�����j�ɋ��܂ꂽ���ϕ���ł��鑊�͕���ɍL�����Ă���B
2�D�����C�����ˏh
�����C�����ˏh������B���ˏh�͏h���҂̑����������c���ƌ˒˂̊Ԃɋ��܂�Ă���A�h��̋K�͂Ƃ��Ă͂����傫���͂Ȃ������B�h��̐��͂���ɂ͕��˂̖��̂��ƂɂȂ������M�ȓs�l�̒˂�����B
1�D���˔����{�E�����R�̗m�ق͂�����B


�����R�i�͂��܂��܁j��������ɂ��āA�����C�����ˏh�E�G�ցB


�����{�O�����_�ō���1�������f�A�����C���ւƌ������B


�O���^���[�̊p����������ʂ肪�����C���B���Ȃ��Ղ�^�������̋����C���i�Ó�X�^�[���[���j�ցB


�Ղ�̊��Ԓ��͕��s�ғV���́A�s���v���U�O�����_�B���ɂ͍���R�i���܂�܁j��������B


�s���Z���^�[�܂Ői�ނƁA���̎�O�������C�����ˏh�̍]�˕������B


���ˏh�̊G�n�}�B���̂����肩�炪�����C�����ˏh�̏h�꒬�ƂȂ�B
���ˏh�͌c���Z�N�i1601�j�ɐ����B�]�˕����\�������A��\�l�����A�������A�������A�����̌ܒ����琬�����B


�]�˕������B
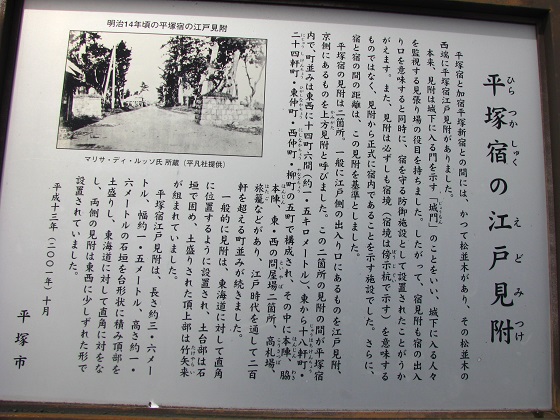
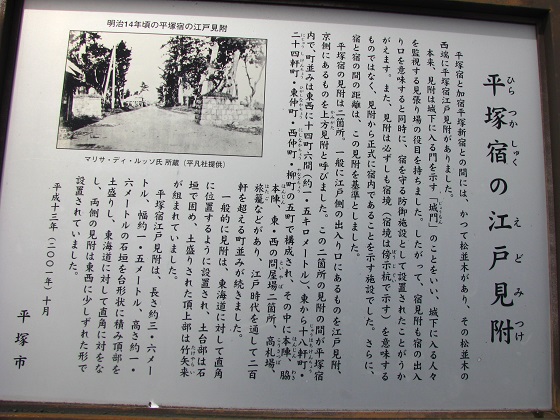
����B
���ˏh�̓����i���͐���j�ɂ͕��ːV�h�i�Ђ�����キ�j���������B
�V�h�͌c���l�N�i1651�j�A�������i��킽�ނ�j�������ĕ��ˏh�̉��h�Ƃ������̂œ����͔����V�h�i��킽���キ�j�ƌĂB�]�ˎ������ɂ͕��ˏh�A�V�h�����킹�Ă��悻2,000�l�̐l�����������B
���݂̃X�^�[���[���͂��̐́A�����������B�����āA�X���̖k���A�쑤�ɂ͍L��ȁu��сi���͂₵�j�v���L�����Ă����B��т͕�s�ɂ�茵�d�ɊǗ�����A��p�Ƃ��Ė��{�̗l�X�ȕ����ɗ��p���ꂽ�B���̍L��ȕ~�n�������ȍ~�A�H�Ɨp�n�Ƃ��Ċ��p����邱�ƂƂȂ�B


�������ɏオ���Ă݂�B


���E���c�����ʂɂ͍���R�i���܂�܁j���傫��������B


�ʂ�̖k���Ɍ��a�m�ܒ��̖ؑ����z�B��������i�����݂�����j�̗m�قɓ��X������ꉮ�i�������j�������ڂ��Ă���B
���̌����͕��ˎs�́u���P�i��������j�����فv�B���Ԃ��Ȃ����a25�N�i1950�j�Ɍ��Ă��A���a39�N�i1964�j����܂ŕ��ˎs�c�����Ƃ��ė��p����Ă����Ƃ����B
���̎p�́A���a�����̌��I���z�ɑ����p����ꂽ�銥�l���i�Ă�����悤�����j�ƌĂ��X�^�C���P�����悤�Ȉ�ہB���邢�́u�ĉ����l���i�v�ɕ`���ꂽ�A�����̉��l�J�`��Ɍ����Ă��������ِ̈l�قł���p��Ԋفu�W���[�f�B���E�}�Z�\������v�ɂ����͋C�����Ă���B�I�풼��̕���������������ɁA���˂̌ւ�������Č��z���ꂽ�̂��낤�B


���͕��s���i�ւ��������邫�j����������g�܂�Ă���B
���ˎs���Ɏc��ߑ㌚�z�Ƃ��ďo�F�Ƃ��v���邱�̌����ł��邪�A�V�������������߂�������̂���邻�����B�s�̃E�F�u�T�C�g�f�ڎ����ɂ��ƁA���C���������ꂽ���̂̎��{�����ɋL�^�ۑ�����ɂƂǂ߂�Ƃ����B
�K�ꂽ���ɂ͕ǂ̃y���L�������班�����A�����h�蒼����Ă����B���g���������Y��ɓh�蒼����Ă���B�u���܂ł��肪�Ƃ��v�ƍŌ�̉��ς��{���Ă���悤�ŁA�n��̐l�X�̐S��Ɏv����v���Ƃ��܂�ɂ��Ȃ��B


�����ق̑O�ɂ��т����i�N�X�m�L�B���j�̑�B
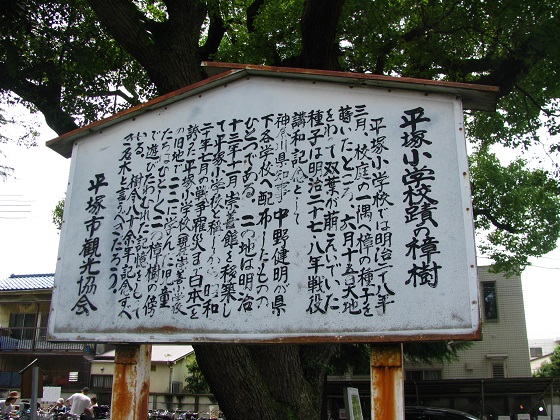
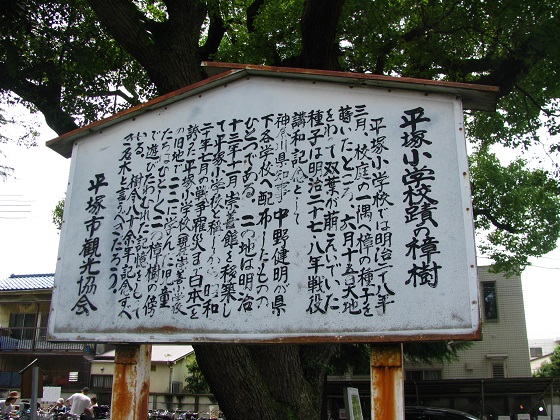
���̖͖���28�N�i1895�j�A�������ˏ��w�Z�̍Z�n�ł��������̒n�Ɏ����ꂽ�킩�������Ƃ���A�n��̋L���ƂƂ��ɕ���ł����B


�Ăы����C���ցB


�e�{�w�ՁB


���ΎԐ����́A���g�≮��i�Ђ������� �Ƃ���j�ՁB


�{�w���ՁB
���ˏh�̖{�w�͈ꌬ�B���ˏh�͏h���҂̑����������c���h�ƌ˒ˏh�̊ԂɈʒu���Ă���A�h�����͋x�e�ɗ�������邱�Ƃ����������B


�E��ɋ�������B


�≮��ՁB


�L�d�́u���C���\�O���V�� ���� ��蓹�i�ۉi���Łj�v�B
�T���Y�i�ڂ��������j�̗��h��̐��[���獂��R��]�ށB


��������茩�鍂��R�B
�����ŁA���˂̖��̗R���ƂȂ����˂����ɍs���B


�����ɓ����čŏ��̊p���E�܁B


���˂̒˂ցB


���ɕ��˂̒ˁB
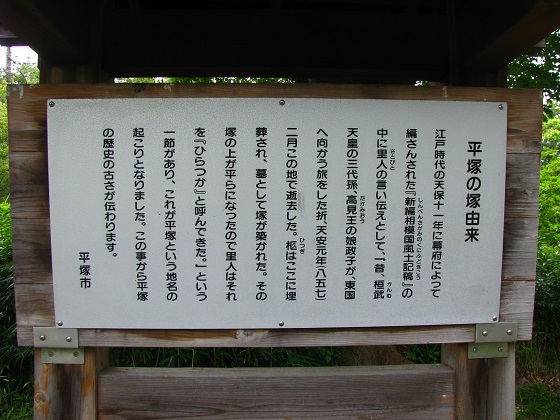
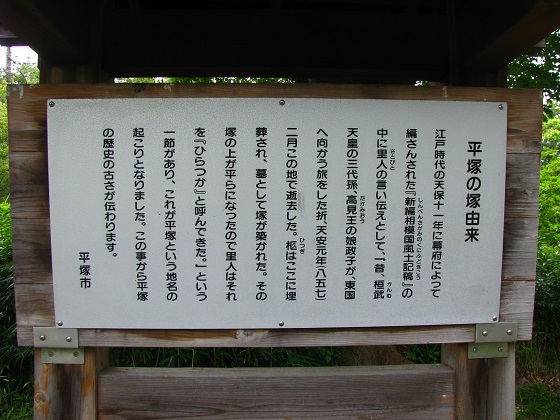
�R���B
���˂̖��̋N����͌Â��B���̒n�Ő����������M�Ȑl�̑���ꂽ�˂��A�₪�ĕ���ɂȂ������Ƃ���u���ˁv�ƌĂꂽ�Ɠ`���B


�˂͐_�Ђ̂悤�ɋʊ_�i���܂����j�ň͂��A���h�ȃN���}�c�������Ă���B
���˂̒˂���A���ˏh�̒���ł������t���_�Ђ������B


���˂̒˂̂����߂��Ɍ��A�t���_�ЁB
�Г`�ɂ��A���v��N�i1191�j���������n����i���͐�j�����{�̂��ߓ��Ђ����������Ƃ���A�Â��͍����{�Ə̂����B���ݒn�ɑJ�������ۂɏt���_�ЂƉ��̂��ꂽ�����̎����͕s���Ƃ����B


�t���_�Ђ͕��ˏh�̒���B
�ޗǂ̏t����Ђ�{�ЂƂ���S���e�n�̏t���_�Ђ͓������̎��_���J��B��ɂ́u�����蓡�v�̖�B


富ҁi������܂��j�̒����B�|���g�����l���ƁA����������l���������Ă���B
�|�Ɛ�Ƃ����ƌ�������́u�����v��A�z���邪�A����͂ǂ̂悤�Ȍ̎��ɂ��Ȃ�ł���̂��낤�B


�����̘e��q�i�킫���傤���j�ɂ́A�t����Ђɂ����Đ_�̎g���Ƃ���鎭�̒����B


�t�����{�Ёi�����_�Ёj�B�l�r�̍T���������������i��傤�� �Ƃ肢�j�B


�t����א_�ЁB������͊���̒��������ԁB
���{�ЁA��א_�Ђ͂�������t�����i�������Â���j�Ō��Ă��Ă���B�t�����́A����̓������؍Ȃ̉������˂��A�ȕǂ̑��𐳖ʂƂ��Č��q�i�����͂��B����o�����݁j���t���Ă���l���B


�t���V���{�B������̛�͓V�_�l�́u�~���v�̖�B


�����哰�B


�t���_�Ђ��狌���֖߂�B


�����ꍆ�ɍ����B���E���c�����ʂցB


�ÉԐ����i�ӂ�͂Ȃ݂����j�M���B���f������n�����Ƃ���ɏ������������B


��������i���݂����݂��B���������j�B
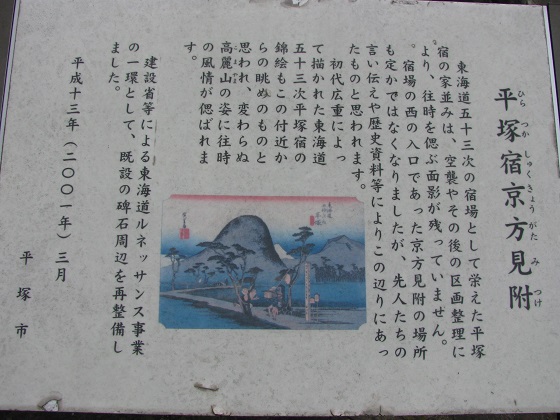
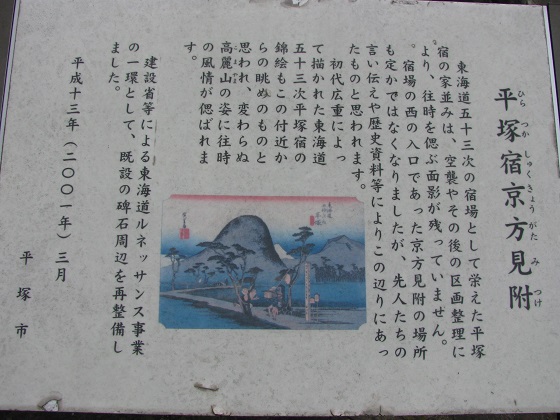
�ē��B


����R��O�ɁA�����C���͑�钬�i���������܂��j�ւƑ����B
���ˏh�Ƒ��h�Ƃ̋����͌����ɂ�����h��Ԃł͍ł��Z���A�ꗢ�i�O�\�Z���j�ɂ������Ȃ���\�����i���悻3�q�j�Ƃ����߂��ł������B
���̃T�C�g���i���jACES WEB �u�V���E�X2�v�ɂ��쐬���Ă���܂��B
