三溪園の四季
三溪園〜盛夏
このページでは二十四節気「大暑」の頃の早朝観蓮会に出向き、茶店で観蓮会限定の朝粥を頂く。観蓮会のあとは内苑・外苑の庭園散歩へ。臨春閣の裏庭を歩き、旧燈明寺本堂の裏手に戦前の三溪園の痕跡、現在とはまた違った姿の名残りを探す。
※平成25年(2013)、平成26年(2014)の画像となります。


八月に入り、暦の上では間もなく立秋。本牧(ほんもく)神社の夏の例祭も間近。


和船に群がる、カモたち。


早朝観蓮会(かんれんかい)が催されていたが、着いたのは九時半。それでも充分に間に合った。


ハスのお花(蓮華。れんげ)の向こうに、観心橋と旧燈明寺本堂。さながら極楽浄土絵図。


翌年の観蓮会は、朝粥を目当てに早朝七時半過ぎに出向く。






薄桃色の、原始ハス。


八時前後、幾つもの大輪が花開いている。




園内の茶店にて早朝観蓮会の開催時のみ提供される、朝粥。






三重塔のふもとの休憩所で朝顔展も開催されていた、とある年。
その時は古建築公開もなく、人出も多くないのでのんびりと庭を見て回ることに。


建物内の人影は研究者か、メディア関係者だろうか。


臨春閣第二屋・琴棋書画(きんきしょが)の間の障壁画「琴棋書画図」。


第二屋の広縁から見る亭しゃ(木へんに射)。


亭しゃから臨春閣・第二屋。松や州浜が絵になる。


臨春閣・第三屋より。


臨春閣の裏庭へ。


ななこ垣に縁どられた、飛び石の園路伝いに。


第二屋・住之江の間の裏庭におかれた、手水鉢。
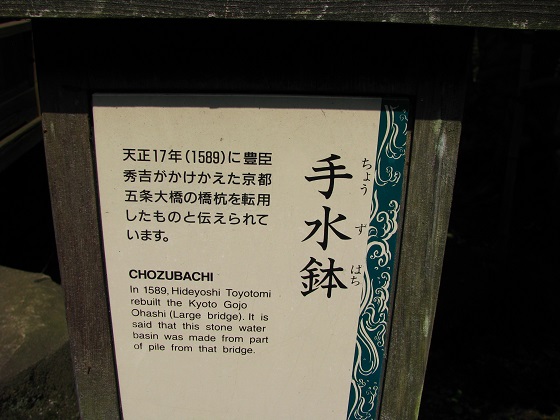
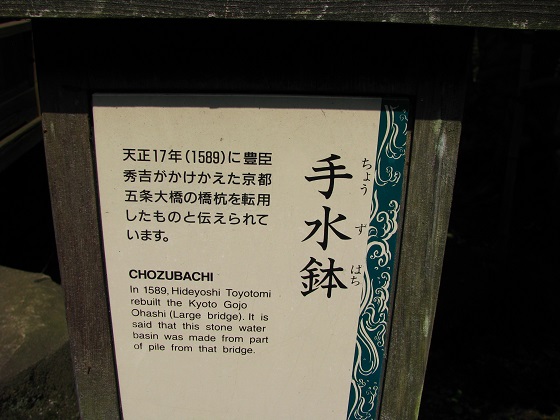


建仁寺垣のついたての向こうは第一屋・瀟湘(しょうしょう)の間の裏庭。身代わり灯籠が置かれている。


竜安寺垣・木戸で仕切られた向こうは、三溪が晩年を過ごした白雲邸。


月華殿・天授院への小径。


水船。


石橋。




茶室の春草蘆へ。


露地(ろじ。茶室の庭)の腰掛待合(こしかけまちあい)。


視線の先は、四つ目垣ではなく背の低い金閣寺垣で仕切られており、その先に置かれている石棺がよく見えるようになっている。しばしの間、名石談義に花が咲きそう。


春草蘆へ。


春草蘆。正面の、光悦垣を伴った小さな茶室の部分がかつて九窓亭と呼ばれた。


ゆっくり鑑賞していたら、何か所も蚊に食われてしまった。


冷房の効いた三溪記念館でひと休み。竹の中庭。


記念館の前庭はかつての池を活かしている。
涼んだところで、外苑へ。


初音茶屋。傍らに、多数の穴が開いた大きな庭石。


寒霞橋(かんかばし)。傍らの石造物は、頭頂部を見ると石幢(せきどう。石塔)のようでもあるが、灯りをともす火袋(ひぶくろ)が見られるので石灯籠のようにも見える。
奥には旧矢箆原(やのはら)家住宅・旧東慶寺仏殿。


渓流に渡された、天然のままの石橋。


左手に林洞庵。右手の渓流沿いに石の祠。
内苑から外苑まで、さまざまな形の由緒ありげな石がさりげなく置かれている。


林洞庵と、奥に初音茶屋。


旧燈明寺本堂へ。


本堂の裏に、石段を伴った古い石垣が。あの石垣の上にはかつて、今は戦災で失われた皇大神宮が建っていた。


かつての鳥居の柱が、今も静かに横たわっている。


旧皇大神宮のパネル。


本堂正面の池。


奥に鶴翔閣(旧原邸)が見える。


観心橋(かんしんばし)。


橋の奥に、三溪園天満宮。


天満宮の位置には、かつて楠公社(なんこうしゃ)が建っていた。


観心橋からの大池。


木陰が心地よい。
このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。
