�ō��i�V�o�U�N���j
����31�N�i2019�j��4����{�BJR���͐��E�����䉺�w��������A���͐�̎ō����ςɍs���B
���͐�̎ō��AJR���͐��̍�����
�u�ō����C���v�͑��͐�̍��ݒ�h�A�V��n��i�V�ˁE�镔�j�̒n������悻1�D4�q�ɓn���Ďō��������B�V�o�U�N�������̌�͑��͐������̍�����ʂ��ĉw�܂Ŗ߂�B�V�鏬�w�Z�M��������H�����ɑ����䉺�w�܂ŁA���悻1km�̍����������Ă���B


���͌��s���ƍ��Ԏs�̋��߂��AJR���͐������䉺�i�����Ԃ��������j�̉w�O�B
���͐�U���H�̈ē��ɉ����Đi�݁A����n���Ă����B���̐�́u�ō��܂�v�̎����ɂ��킹�ė��Ă�ꂽ����ւ̓�����ׂƂȂ�B


����ɗU������ł����A�u�ł����烉�C���v�܂ł͉w����15���قǁB


�����₩�ȎR�e�̒O��R�i���킳��B1567m�j����h������O��O�c��̗Ő��A���̉��ɂ͒O��ō���̕g���x�i�Ђ邪�����B1673m�j�B


�����Q���̍L����A�t�̓c��ځB


���q�T�b�J�[�Ȃł������[�O�E�m�W�}�X�e���_�ސ쑊�͌��̃g���[�j���O���_�A�m�W�}�t�b�g�{�[���p�[�N�B


�ł����烉�C���ɓ����B




���ԏ�̉��ɂ��т���[���ȎO�p�`�̑�R�i������܁B1252m�j�B
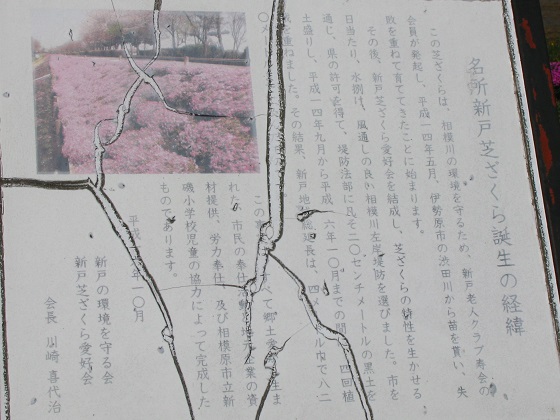
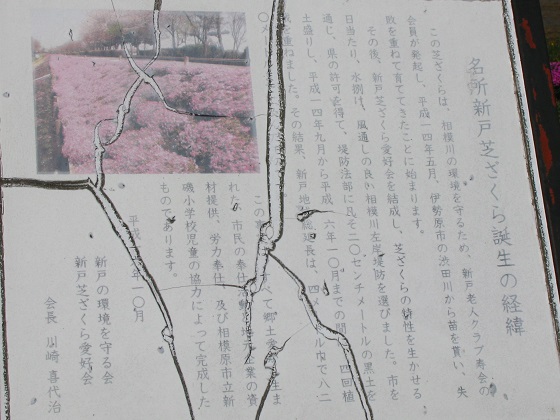
�ē��ɂ��ƐV��i���炢���B�V�ˁA�镔�j�n��̃V�o�U�N���͕���14�N�i2002�j�A�u�V�ˁi����ǁj�ł����爤�D��v�̐l�������ɐ����E�a�c�삩��V�o�U�N���̕c���Ĉ�Ă��̂��n�܂�A�Ƃ���B���݂̑�����1�D4�q�͑��͌��s�̌����T�C�g�ɂ��Ɠ��{��̒����A�Ƃ̂��ƁB


��h���A�Z���s���N�̃V�o�U�N���B


�I�Ղ��}�����\���C���V�m�Ƃ̋����B




�͐�~�ɂ͌܌��̘A�x���ɍÂ����u���͂̑���܂�v�ŗg�������̍��g�݂�������B




�W�����̃V�o�U�N���B




���։��ւƉ��тĂ����A�V�o�U�N���B


���c��̃X�C�Z���B


�x�m�R�ƔE�씪�C�����`�[�t�Ƃ����A�ł�����K�[�f���B


�c�̔̔����s���Ă���͗l�B


�ЂƂ����ɃV�o�U�N���ƌ����Ă������Ƒ����̕i�킪����B


�u�ł�����x�m�v�Ƒ�R�̋����B






�����̖c��ȘJ�͂��y�����邽�߁A�h���V�[�g���ăV�o�U�N����A�����@�������Ɩڂɂ���悤�ɂȂ����B���N������V�[�g�̓V�o�U�N���ł݂�����ƕ����s�������B


�������������Ɨ���鑊�B��̑�́A���͐�B


�O��R�����]�B


���������ʁB


���镔�n��̃V�o�U�N���B


���Ɛ��N������A��������݂�����ƍ炫�����B


�V�o�U�N�����̂��̂̐����X�s�[�h���i��ɂ���č�������B








�^�������V�o�U�N���͏t�̒W��̂悤�B




�傫�ȋ������ݒu���ꂽ���B�����̓X�C�b�`�o�b�N�̂悤�ɐ܂�Ԃ��đk�サ�Ă����`���ɂȂ��Ă���B




�u���͐앚�z�i�ӂ������j�v�̃��j�������g�B�����瑤�Ŏ搅�����_�Ɨp����Ί݂ɑ��邽�߂Ɏ{�H���ꂽ�B
�����z���Ƃ͗p���H���͐�ƌ�������ۂɉ͐�̉�����点�ĉ��点��H�@�B�T�C�t�H���̌������g���ΐ��̗���̏o����������Ⴍ���邱�Ƃŕ����グ��悤�ɐ��𗬂����Ƃ��ł���B


�E�艜�Ɉ镔����H�i������ �Ƃ����ケ���j�̉��A��O�ɋ����B�����ɓ��O��O�q�ɍ����鍂��R�`���ʎR�i�Ԃ�������B747m�j�`�o���x�`�،��R�̎R����]�ށB
����H�Ƃ͍k�n���������߂̔_�Ɨp�����搅����{�݁B�㐅���֘A�{�݂ł���Ύ搅���ƌĂ�Ă��鏬�^�_���̂悤�Ȃ��́B
���B�̕�Ȃ��A���͐�B�㗬�̃_�����牺���̎搅���܂ŁA���̐��͍��x�ɗ��p����Ă���B���͐�̗��悻�̂��̂͌����ł͌������Ɍ����邪�A�����Ƃ����_�ł͐_�ސ쌧�������ɂƂ��Ă����������Ƃ͂ł��Ȃ��B


�镔����H�����ɓ����B�����Ńg�C���x�e�B


���������͑��͌��s�ό�����u���͐�ł�����}�b�v�v�Ɍf�ڂ��ꂽ���[�g�ɉ����āAJR���͐��̍����ցB


�\�����̍��B


�V�鏬�w�Z�̐M���B���̂����肩��O�サ�āA���悻1�q�ɓn����H�����̍����������B


���H���A���̃g���l���B








�u��̗����炢���v�̕ǖʂ�����A���͂̑���̃^�C���G�B�ٓ��ɂ́u���͂̑���Z���^�[�v�����݂���Ă���B






��R�ƍ��B




���H�ɉ�����1�q�������A�����B����n��Ƒ����䉺�w�͂����B
���̃T�C�g���i���jACES WEB �u�V���E�X2�v�ɂ��쐬���Ă���܂��B
