三島から箱根八里・西坂
山中城跡
(2)山中城北の丸・本丸・二の丸(北条丸)・宗閑寺

山中城西の丸と障子掘、西櫓。

ここまで出丸から主郭の西櫓までを巡ってきた。この先は帯曲輪(外周路)から北の丸・本丸へ向かう。

埋もれた西の丸障子掘。


帯曲輪の外側は、自然の谷が深い空堀となる。


埋もれた畝。

ローム層剥き出しの外周路。

元西櫓は本丸の跡で巡ることにする。

溜池。
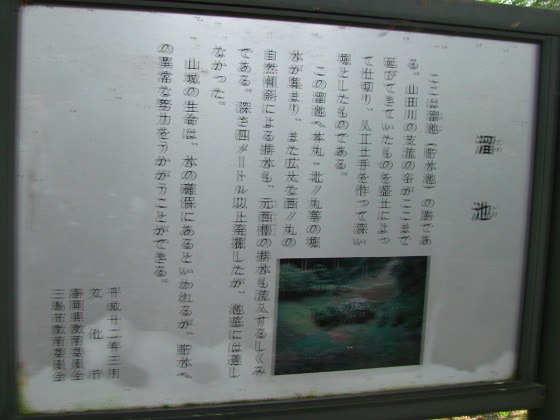
溜池は自然の谷を仕切って堀とした。ここには西の丸の堀、元西櫓の堀、本丸・北の丸の堀からの排水が集まってくる。
このように山城では水の確保に力を注いだ。

北の丸・本丸へと登っていく。

帯曲輪(外周路)の北側は深い谷。


そして谷の反対側に本丸北堀。年月を経て埋もれているが、昔は相当深かったのだろう。
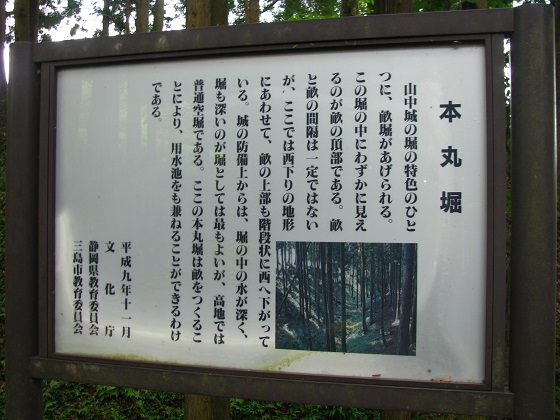
畝の頂部を確認するのはちょっと難しい。

北の丸に到着。
北の丸は城内でも高所に位置する。標高は583mあり、この平場自体が西の丸物見台よりも高い。
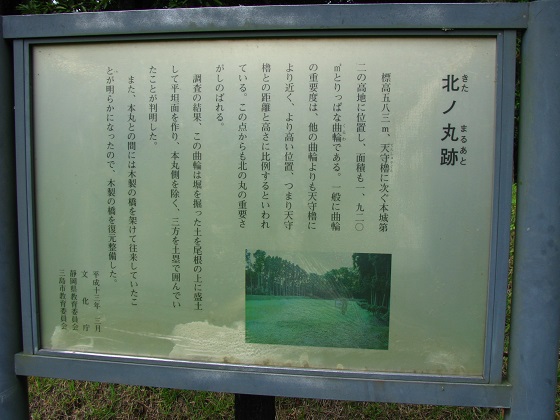
広くて立派な曲輪。

非常に深い、北の丸堀。

これでも築城当時より相当浅くなっているそうだ。
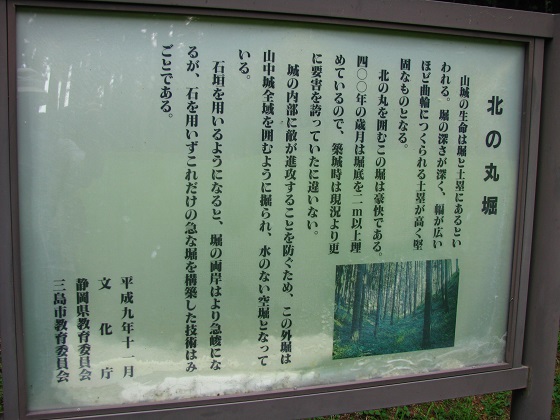
解説板。

三方を土塁に囲まれた北の丸。

本丸北橋。北の丸と本丸をつなぐ。

橋で跨ぐ本丸北堀は、長い年月を経て相当浅くなっている。
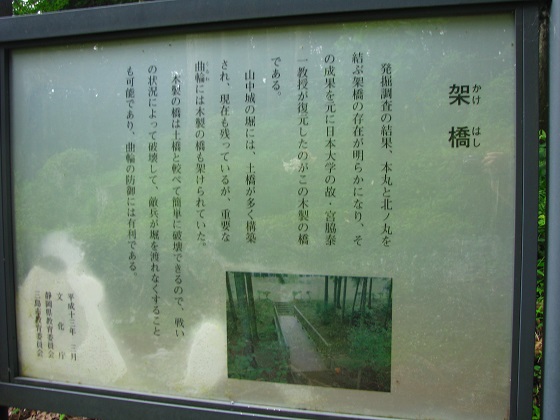
北の丸が落とされそうになれば、この橋を壊して本丸を死守した。

本丸隅櫓の天守櫓へ。

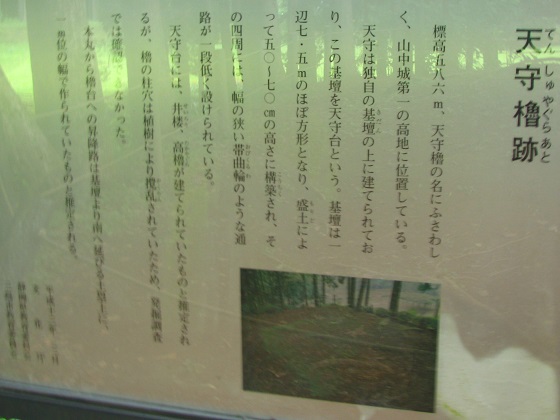
天守櫓(天守台)。城内最高所(586m)。井楼(せいろう)、高櫓(たかやぐら)が建っていたと推定されている。
ここが、城内の鎮守であった諏訪神社を祀った「諏訪壇」であったという可能性はないだろうか。

天守櫓から見る北の丸。

天守櫓から見下ろす本丸。合戦時には城将・松田康長が布陣したとされる。
本丸へ下りる。
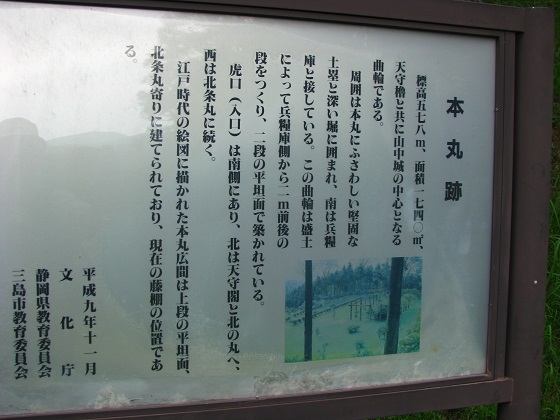
本丸の標高は578m。藤棚のあたりに本丸広間が建っていたようだ。

矢立の杉。
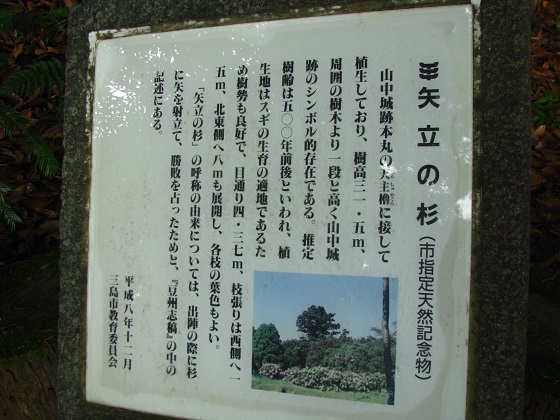

本丸の曲輪は段差のある二段の平場となっており、一段低い平場は兵糧庫・弾薬庫となる。

そして祠。

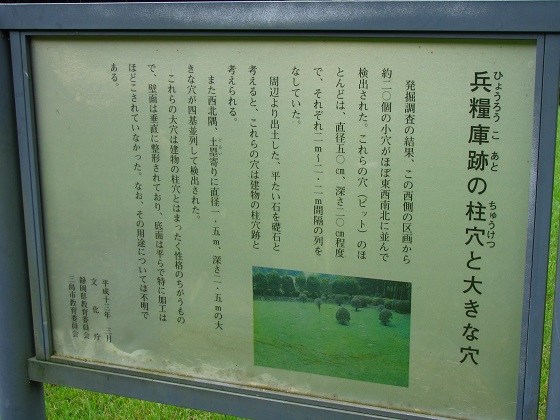
この平場では謎の大穴が発掘されている。

諏訪神社と駒形神社を合祀した、駒形諏訪神社。
諏訪大明神は東国における武門の守護神として崇められた。諏訪といえば武田信玄が諏訪頼重の信濃を侵攻して領国に組み入れているが、小田原北条氏の城においては初期からの支城である玉縄城(たまなわじょう。鎌倉市)に伊勢宗瑞(いせ そうずい。のちに北条早雲)により諏訪大明神が勧請されている。そして、ここ山中城でも守護神として祀られた。
駒形神社は江戸時代、山中が東海道の間の宿(あいのしゅく)として栄えた頃の勧請だろうか。案内板には「山中城の落城(1590)後、人々移住し箱根山の往還の宿場として栄えた」とある。
この場所は旧街道から入ってすぐのところ。合祀にあたり、村人の手によってここに諏訪神社を移転し駒形神社と併せて祀ったという可能性はないだろうか。

立派なアカガシ。樹齢は推定650年。
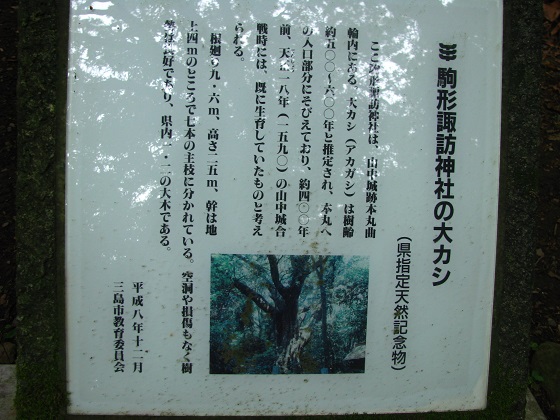
案内板。県内一、二の大木とあらば、三島の隣りの函南町(かんなみちょう)で更に巨大なアカガシを目の当たりにしたことが思い出される。

本丸西橋(木橋の手前は土橋となる)から二の丸(北条丸)へ。こちらの木橋も本丸を死守する際には壊して落とすことになる。

土橋から南側に見る、本丸西掘。
二の丸側には堀障子(畝)の高さに「犬走り」が巡らされている。堀は屈折したクランク(横矢折れ、折邪・おりひずみ)となって先へ続く。

土橋の北側。堀は薬研堀(やげんぼり。V字状の堀)が掘られ、本丸西堀はここで堀止めとなる。
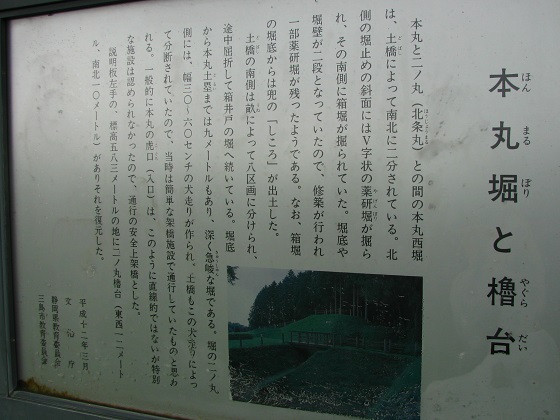
本丸西堀の解説板。

クランクの続き。箱井戸の堀へと続いていく。

二の丸(北条丸)は大きな曲輪。南に向かって傾斜している。二の丸には応援に入った北条氏勝(第六代玉縄城主)が布陣した、ということになろう。

二の丸の隅櫓から覗きこむ、二の丸北堀。
堀の向こうは先ほど西の丸から北の丸へ向かって歩いたあたりだろうか。

隣りへ視線を移すと本丸北堀、奥には北の丸。


もう一つの隅櫓、二の丸櫓台へ。

小さな元西櫓を見下ろす。その奥には、最初に歩いた西の丸障子掘と西の丸が見える。

二の丸。

二の丸虎口(こぐち。出入口)と元西櫓へつながる木橋(二の丸橋)。
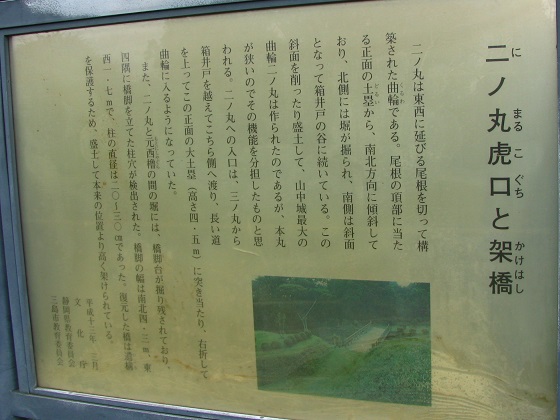
二の丸(北条丸)の解説板。
巨大な二の丸は本丸の機能を分担したと考えられている。

二の丸から二の丸橋を渡って元西櫓へ。

二の丸橋の南側の堀。

二の丸橋の北側の堀。左は元西櫓。堀の左奥は先ほど見た溜池へと通じる。

小さな曲輪の元西櫓。奥には西の丸と西の丸物見台。
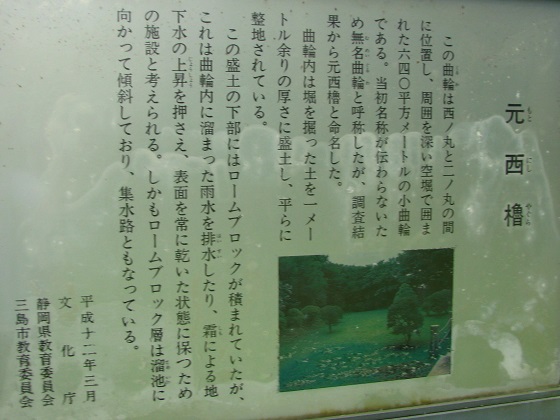

二の丸(北条丸)虎口から箱井戸・三の丸へ。


箱井戸。画面奥の道は宗閑寺(三の丸跡)へと続く。
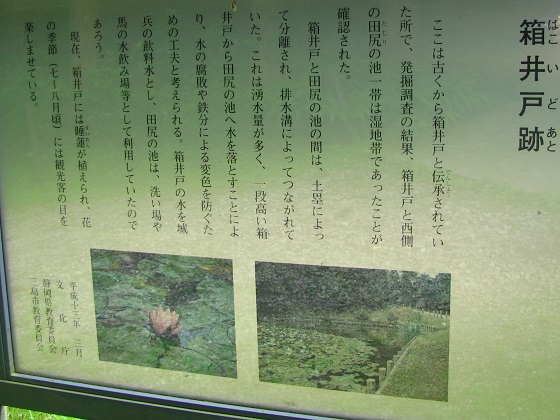
箱井戸の解説板。

箱井戸の水は城兵の飲料水となったと推測されている。この向こうが、一段低い田尻の池につながっていた。

宗閑寺へ。

山中公民館と宗閑寺のお堂が建つ。ここは三の丸跡となる。

宗閑寺(そうかんじ)。
宗閑寺は山中城副将を務めた間宮康俊の娘(後に家康の側室となる)が山中城の戦いで討死した父の慰霊を祈願、その遺志により落城から30年後の元和六年(1620)に開かれた、と伝わる。
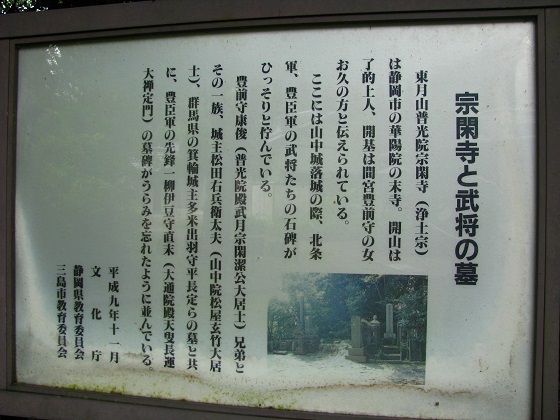
最後に城将、敵将の墓を参る。

右の石柱は城将・松田康長(まつだ やすなが)の墓。
松田康長は小田原北条氏三代(氏康・氏政・氏直)に仕え、本城直属の御馬廻衆などを歴任した家臣。城が落ちる直前、共に城を守った第六代玉縄城主・北条氏勝(ほうじょううじかつ)を逃がして自らは討死した。
左の五輪塔は間宮康俊(まみや やすとし)と一族の墓。間宮氏の家紋「四つ目結(よつめゆい)」が見られる。
間宮康俊は小田原城の支城である玉縄城(たまなわじょう。鎌倉市)の配下・笹下城(ささげじょう。横浜市港南区)の城主であり玉縄衆(たまなわしゅう。玉縄城に属する軍団)の一員。間宮氏は初代早雲の頃から仕えていた譜代の家臣であり権現山城の合戦(横浜市神奈川区)における奮戦の記録も残る。
康俊もまた、玉縄城三代城主北条綱成(ほうじょうつなしげ。宗家第二代氏綱の娘婿、氏康の義弟)の頃から仕えていた老将であった。合戦では岱崎出丸を守備し、討死した。

案内板に見られる、群馬県の箕輪城主多米出羽守平長定らの墓。
多米長定(ため ながさだ)は上野(こうずけ)・箕輪城(群馬県高崎市)が小田原北条氏の城となった時代(天正10・1582〜)の城代(じょうだい)。城主・北条氏邦(ほうじょううじくに。宗家第四代氏政の弟。本拠は武蔵・鉢形城)の留守を預かった。
多米氏もまた早雲の頃からの譜代の家臣。小机城の配下となる武蔵・青木城(横浜市神奈川区)を本拠としたと伝わり、所領の三ツ沢に豊顕寺(ぶげんじ)を開いている。

一柳直末(ひとつやなぎ なおすえ)の墓。
一柳直末は秀吉の家臣であり美濃・軽海西城(かるみにしじょう。岐阜県本巣市)城主。別手隊の指揮を執り城の西南(西の丸側)を攻めたというが、鉄砲に撃たれて討死した。
山中城の合戦は、秀吉方の将である中村一氏(なかむらかずうじ)の配下で参戦した渡辺勘兵衛により「渡辺水庵覚書」が記された。これにより合戦の生々しい様子が後世に伝わった。

こちらの一角は誰の墓だろうか。僧侶の墓に用いられることの多い無縫塔(むほうとう。卵塔)が数基見られるので、おそらくは歴代住職の墓ということか。

山中城を後にして箱根旧街道に戻り、再び箱根峠をめざす。

